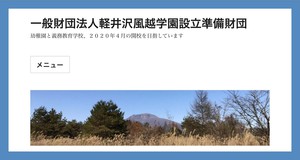軽井沢風越学園の情景を更新しました。
今回追加したのは「自己主導の学びと協同の学びのゆるやかなつながり」「ライブラリーとアトリエ」の2つ。
軽井沢風越学園の情景 http://kazakoshi.jp/scene/
「自己主導の学び」の背景には「自己主導の遊び」があります。
この8年間、森のようちえんぴっぴという幼児教育の現場にびっちり関わり、子どもたちと森で時間を重ねてきました。この経験は本当に貴重なもの。この経験していなかったら、軽井沢風越学園設立という動きはなかったと思う。
ぴっぴでは、遊びを大事にしている。遊びが中心。
「はい、今日は〇〇遊びをしますよ。」「この後は、お散歩するよ!」「じゃあ、みんなで崖登りしてみよう!」なんていう大人が主導する遊びではない。だいたい、大人がそんなふうに関わるのは遊びじゃなくてプログラム。
この8年間で子どもたちが遊びの中でたくさん「自己決定」している場面に出くわした。というよりも、遊びって自己決定の経験の連続、積み重ね。いわゆる一斉保育やプログラム的な幼児教育・保育だと、その機会は奪われる。たっぷりとした遊びの時間と環境が確保されることが幼児期には何よりも大切。
今日は何しようかな、誰と遊ぼうかな、どこ行こうかな、どんなふうに過ごそうかな...。そんな思いを抱きながら登園してくる子どもたち。
先に来た子が崖に登っている。
泥遊びしようと思っていたけど、ちょっと考える3歳児。
「僕も崖登りしてみよう。ちょっと怖そうだけど...。」
崖の下に立ってみる。見上げると5歳児が「こっち側の方が登りやすいよー!」と声をかけてくれる。
「今日は、登ってみよう。」
登り始める。思ったより登れる。でもまだてっぺんまではしばらく先。
目の前に細い木の根っこが出ている。
「これにつかまっても大丈夫かな?抜けちゃうかな?」 考える。
そしてつかむことを決める。
「あ、大丈夫だった。抜けなかった...」
下を見る。けっこう高い。怖い。
「やめようかな...。降りようかな...。でも、もうちょっとだけ登ってみよう」
あ、片方の長靴が脱げた。長靴は下まで落ちてしまった。
「ど、どうしよう...。」
迷う。
「いいや、こっちも脱いじゃえ。靴下ドロドロになってもいいからこのまま登っちゃおう!」
上から声が聞こえる。
「レスキューいきますか?」5歳児の子が声をかけてくれる。
助けてもらえるとうれしいな。でも自分で登りたいな...。
「大丈夫!」
「わかったー。やばかったら助けてー!って叫べよ!」
「はーい!」
遊びを通じて、「今、自分はどうしたいか」「これからどうしたいか」「この前はできなかったけど...。今日はこうしてみよう」 いろいろな自己決定を繰り返す。自分の時間をどう過ごしたいか、自分で決める。
そんなふうに遊びを自己主導した経験を積み重ねていき、その延長戦上で学びも自己主導していく。
協同の学びのベースになる経験も遊びの中から。遊びを通じて仲間と関わりを重ね、深めていく。ぶつかりあったり、助け合ったり。相談、話し合い、対話というのも遊びの中で自然に生まれてくる。その糸がもつれた時には大人が手を貸す。
今回の情景の背景には、そんな幼児期の遊びの経験の積み重ねがベースとして存在しています。